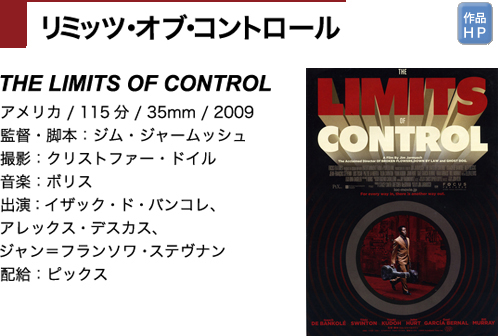 |
こういう作品を作る格好良い大人がいるなら、世界は変わっていけるのかもしれない、と思えた2009年度の傑作。 迫力のある音と共に心震わせ号泣した。(事務局S) いつまでたっても『コーヒー&シガレッツ』のようなグズグズとした会話ばかりで、一体この短編の連続のような映画は何かと思っていると、 一気に物語は急転する。その小ささと大きさのスケール感の過激な接合に心躍る。ボリスが作り上げた、『デッドマン』を思わせる金属質の 音響が映画のそこかしこに貼ついて、ふたつの世界がこすれあう軋みの音を響かせる。その間を駆け抜けよと、それらは語りかけてくる。 |
 |
ダニー・エルフマンのストリングス&サックス、プッチーニの「トスカ」、ボウイの「クイーン・ビッチ」、そしてスライの「エヴリデイ・ピープル」など楽しみなところはたくさんあるが、この映画を爆音にして一番拡がる音は、その時代の人々の“ 歓声” ではないかと思う。(バウスシアター・スタッフ) 70年代前半、世界は未だゲイに対して不寛容であった。ラヴ&ピースはゲイの人々にとってはまだまだ遠い未来の話。その不寛容に対する闘争は、しかしストレートな男たちのそれとは違い、どこか柔らかく愛と親密さに満ちていて、ただ、それゆえに痛みも大きい。その悲しみと希望の歌が高らかに歌われる。小さな闘争と、小さな愛と、小さな痛みとが触れ合ってビッグウェーブを作り出す、その運動のざわめき。 |
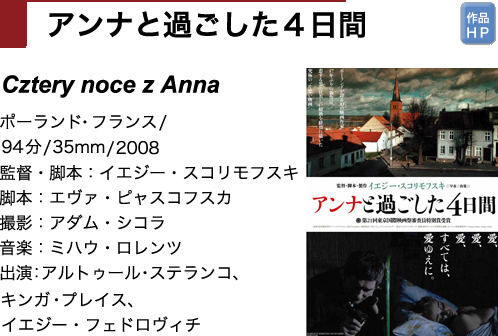 |
こんなにも目と耳をフルに使って観てしかも泣いた。ハッとする瞬間の連続に映画を観る歓びを改めて教えてもらった一本。爆音でど うなるか楽しみすぎる! アコーディオンの不協和音や、部屋の額縁から流れる小川のせせらぎから、今度は何を感じるだろうか。(バウスシアター・スタッフ) 分厚い雲に世界が閉ざされるポーランドの秋の終わり、冬の始まり。その陰鬱な空気の中での4 日間の物語には、もはや救いはない。貧しき者、虐げられた者たちの魂の拠り所は一体どこにあるのか? しかしそんな貧しさと痛みの物語がスコリモフスキによって語られるとき、映画は一気に豊かなものとなる。そのゴージャス感! もちろん、そのマジックには音が最大の貢献をしていることは言うまでもない。 |
 |
イギリスが舞台の映画だから、ロックばかりが流れるのかと思えば、スペシャルズや、パーシー・スレッジ、アップセッターズ、メイタルズ、などかっこいいサウンドばかり。流れる音楽からシーンひとつひとつの意味を感じることが出来るところがいい!(事務局O) 80年代前半。不況にあえぐ英国は、サッチャーの強権に未来を託した。悪ガキたちも音楽も、みんな切羽詰っていた。そこから生まれた音楽。これがイギリスだという強い肯定と、これがイギリスというアイロニカルな視線とが交じり合い、未来は幻想の彼方へと沈む。そこから聴こえてくるのがパーシー・スレッジの「The Dark End of the Street」。ごりごりのアメリカ南部音楽である。この皮肉もまた、英国映画というべきだろう。 |
